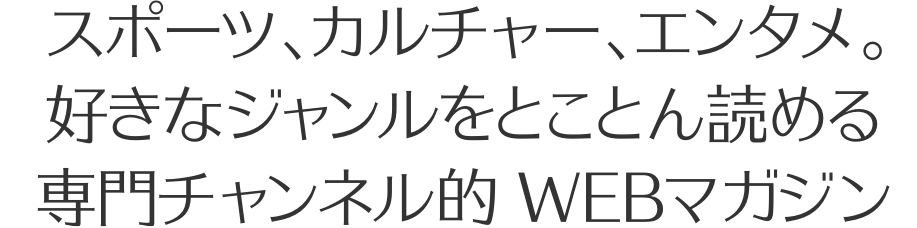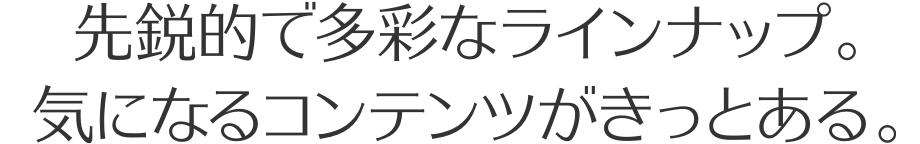【無料記事/オフ企画】ネイサン バーンズとFC東京をめぐる伴和曉の冒険<1>(2017/07/10)

伴和曉通訳。
伴和曉ははじめからネイサン バーンズの通訳だったわけではない。バーンズがFC東京に加入した2015年の夏、伴はカンボジアのクラブチームでボランチとしてプレーしていた。「2022年までは現役にこだわりたい」と言っていたはずの、“現役バリバリ”である伴がなぜスタッフとして東京へとやってきたのか。まずはそこを紐解かなければ、バーンズとの友情が生まれた発端にたどり着かない。
伴は2016年初頭のようすを述懐する。
「2015年までプレーしていたカンボジアから2016年シーズンは離れようと考えていました。2年半もいるとレベルや環境などカンボジアのサッカーに関してはだいぶわかるようになり、より成長できる環境に身を置こうという思いからでした」
8月21日生まれの伴は当時まだ28歳。もちろんプロとして限界を感じる年齢ではなかった。
「東南アジアでサッカーをつづけることはできると思いました。35歳、40歳になっても同じレベルで活動するなら、それなりの地位は築けるだろうと。ただ、上をめざさないのにプロ選手をやる意義を見いだせなかった。たとえば、ここで活躍すればより上のカテゴリーや上位チームに移籍できるとか、代表に選ばれるとか、そういう道筋が見えないまま、ただ長く現役をつづけることにプライオリティを置くことができなかったんです。もちろんサッカーは好きですし、プレーしたほうが楽しいのは当然なんですけど、選手としてやるなら常に上をめざすという条件がぼくのなかにあったので」
新天地の候補に挙げていたのは、メジャーリーグサッカー以外にも多くの国内リーグを持つアメリカ合衆国、そして日本である。
「もっと英語をやりたいと思ってアメリカでトライアウトを受けると同時に、トップカテゴリーでプレーしたことがなかった日本国内でもクラブを探したんですよ。でも日本はプレーヤーの移籍先が決まりづらい時期でしたし、アメリカも返事待ちだった。いちばん嫌なのはフリーの状況になることです。半年間、一年間所属がないことは自分の年齢を考えると嫌でした。ならば、選手ではなくとも日本のサッカー界に一度加わり、一年間活動するうちに、もう一回現役に戻りたいのか、身を引いてちがう路に進むかを考えようという意味合いで、(たまさか)引き合いのあった東京にスタッフとして来ました。
その2016年春の時点ではプレーヤーでいたいなという思いもありましたし、いまも正直、現役を諦めた気持ちではないですけど、ことし(2017年)も東京に残りたいなと思った理由のひとつはバーンズだった。彼が東京に残りつづけるかぎりは、ぼくは彼の支えになりたいという思いがありました」
東南アジアの強国となりつつあるタイでプレーする話もあったという。しかし自分にしかできない体験をしたいからこそ、他の日本人選手があまり活動していない国でボールを追おうとカンボジアを選んだ伴にとっては、既に日本人選手が多くのチームに散在するタイへ行くとなると、動機が弱かった。多少、水準の差はあっても、カンボジアもタイも同じ東南アジアであり、本質はさほど変わらない。日本に近いリーグ運営のシステムを採っていて競技レベルが高いタイでの活動にも相応の意義はあるように思えるが、伴は「魅力を感じなかった」と言う。それは「自分でも不思議」だと伴は付け加えた。もしかしたら、カンボジアで吸収した以上の新しい発見がないことを鋭敏な感覚で悟っていたからなのかもしれない。
「もしいい話があれば、いますぐプレーヤーに戻りたいなという思いは正直あります。ありますけど、いまトライアウトを受けて日本でフットボールを、とは思っていません。それは、選手ではなくともサッカー界に貢献できるということがわかっているからかもしれません。プレーヤー以外の生活をしたときに自分がサッカーに対してどういう思いを抱くのかを知るのも、通訳を始めるときに楽しみにしていたことですし。
J3の練習にも、たまに入ったりするんです。『おっ、伴くん現役復帰?』みたいに冗談を言われたりもしますけど(笑)。その瞬間のスポットでのテクニックや判断については自分でも『やれるな』と思うときはあります。でもそれを一年間フルでやり通して戦いつづけるのはなかなか容易ではない。彼ら(東京の選手)は身体能力に恵まれていますが、自分は経験に基づく状況判断や、どうしなければいけないかという術を導き出す思考力で生き残ってきた。そこだけに関してはまだまだやれると思います」
頭を使い献身的に働くことで己を磨き、価値を高めてきた伴には、そうした考えるプレー、献身的なプレーが不足しがちな東京の現状にもどかしさをおぼえることもある。だから選手に求められれば、伴は躊躇なく引き出しを開けて材料を提供する。監督でもなくコーチでもなく選手に近いフラットな立場の彼にしか伝えられないことを伝えるために「できるだけ選手の話を聞き、チームのために自分ができる立ち位置でやりたい」と、伴は言うのだ。いつの間にか、それだけチームへの思い入れが強くなっていた。そしてその核となっていた人物こそ、ネイサン バーンズだった。
「バーンズがいるからぼくはここにいる、彼が去るまではいようと思っていました。しかし3カ月前にウタカという新しい存在が来た。途中で放り出していなくなるのもよくないと思いますから、少なくともことしはいると思います」
<つづく>
———–
■後藤勝渾身の一撃、フットボールを主題とした近未来SFエンタテインメント小説『エンダーズ・デッドリードライヴ』(装画:シャン・ジャン、挿画:高田桂)カンゼンより発売中!
◆書評
http://thurinus.exblog.jp/21938532/
「近未来の東京を舞台にしたサッカー小説・・・ですが、かなり意欲的なSF作品としても鑑賞に耐える作品です」
http://goo.gl/XlssTg
「クラブ経営から監督目線の戦術論、ピッチレベルで起こる試合の描写までフットボールの醍醐味を余すことなく盛り込んだ近未来フットボール・フィクション。サイドストーリとしての群青叶の恋の展開もお楽しみ」
———–